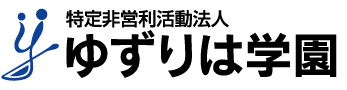潮風の電話
三河湾を望む田原市の高台。赤い木製の電話ボックスの中に、電話線がつながっていない黒電話が一つある。
設置したのは、沓名(くつな)智彦さん(66)と和子さん(69)夫妻。二〇〇一年、教師だった和子さんが、多様な子どもを画一的に指導する学校教育に限界を感じ、退職してフリースクール「ゆずりは学園」を画家の智彦さんと開いた。
県内に住む女子生徒が通い始めたのは三年後。小学生の時、先生と合わず不登校になり、他人に甘えられない、本音が言えない自分に苦しんでいた。当時は中学二年生。「なぜ生きていないといけないのか」と自殺未遂を繰り返していた。
家に泊まらせたり、カウンセリングをしたり、寄り添い続けた。だが、〇九年一月、生徒は自宅で自殺。遺書には「これ(自殺)に失敗したら生きるから」と書かれていた。
「本当は生きたかったんだ。生きづらい社会にしたのは、私たち大人の責任。私たちが彼女を死なせてしまった」。学園をやめようとさえ思ったが、生徒の両親に「やめないで」と頼まれ、踏みとどまった。
生前の希望に従ってお墓はつくられず、「ずっと心の整理がつかなかった」と智彦さん。そんな時、岩手県大槌町にできた「風の電話」を知った。東日本大震災で亡くなった人と残された人を結ぶ電話として広まっていた。
生徒が亡くなって十年目の今年六月、解体業者から譲り受けた電話ボックスにペンキを塗って仕上げ、学園の敷地に建てた。初めて受話器を取った時、生前はつかめなかった彼女の本音が聞こえた気がした。語り掛ける場所ができ、ようやく心が落ち着いた。
時折、電話ボックスに寄っては「元気?」「救えなくてごめんね」などと話し掛ける。パンを焼くのが好きな優しい生徒だった。「いつも、そこに、あの子がいるように感じる」と和子さんはほほ笑む。
夫婦が支援した親子は三千人を超える。雨の夜、ずぶぬれになって家出した子どもを捜したり、ファクスを何十回もやりとりして親の苦しみを受け止めたり。「あの子がいたから、続けてこられた。もう二度と、あんな悲しいことは嫌」と智彦さん。電話は、夫婦だけのものではない。「私たちと同じように、大切な人を亡くした人に自由に使ってほしい」
<風の電話> 岩手県大槌町の海を望む高台にある電話ボックス。電話線がつながっていない黒電話が置かれている。ガーデンデザイナーの佐々木格(いたる)さん(73)が自宅庭園に設置。2011年3月の東日本大震災の後、遺族らが会えない相手に思いを伝え、しのぶ場となった。これまで国内、海外から約3万人が来訪。以前は木製だったが、老朽化のため、今年8月に全国からの寄付金でアルミ製に交換された。